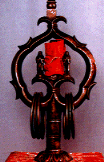
創建は治承3年(1179)、長井庄司斉藤氏の3代目斉藤別当実盛が自己の守り本尊の大聖歓喜天をまつって聖天宮と称し、長井庄の総鎮守としたのに始まります。その後、実盛の子、実長(良応僧都)らが聖天堂の修復と別当寺院建立の請願をたて、建久8年(1197)に本堂を修復し、さらに歓喜院長楽寺を建立しました。そして歓喜院に11面観音を本尊として安置する一方、環内中央に歓喜尊天を配した「御正躰錫杖頭」を奉鋳して、聖天宮の本尊としました。
現在は本殿は、25年の歳月をついやして宝暦10年(1760)に完成したもので、壁面を飾る華麗な彫刻は桃山時代の建築様式を伝える貴重な遺構として、本尊の錫杖とともに国の重要文化財に指定されています。このほか堂々たる威容を誇る貴惣門をはじめ、室町初期に当地方が「福河庄」と呼ばれていたことを示す鰐口、中国製の絹織物「紵絲斗張」などの貴重な文化財も数多く残されています(右の図は本尊の錫杖頭)。
江戸時代の妻沼は、新田住環(現在の県道太田熊谷線)の宿場として栄え毎月5日と10日には市が立つなど大変な賑わいを見せ、上州へ向かう途中の徳川家康が参詣したとの記録も残されています。

