|
さて、ここは静かな住宅街の中でも、ちょっと大きめの敷地をもつ一角。 「えぇぇ〜〜〜!!? 『また』昼寝して帰ってきちゃったのぉ!!?」 …いや、少しだけにぎやかな住宅街。大声の主・アメリアが、言葉と同時にテーブルへ勢いよく手をつく。 「そおよ。悪い?」
テーブルの向かいで、リナはショートケーキをひとかけ口に入れていた。
「いつもの事じゃない。なんにもおかしくないわよ。
リナは呆れながら香茶をすする。ケーキの味に慣れ、甘ったるくなってしまった口の中が、香茶の風味と同じくすっきりすがすがしくなった。 「…ガウリイ神父って…町の女性たちに人気あるのよねー……」 カップをかたむけるリナの手が、ピタリと止まる。そ知らぬ顔でアメリアは続けた。
「礼拝の時にいつもご挨拶するけど、格好いいし礼儀正しいし。わたしもアタックしてみようかなあ?」 慌ててソーサーにカップを置きながら言いつのるリナを見て、アメリアはにっこりと笑う。
「はいはい、わかってますって。リナの大事な人に、手なんか出さないわ♪」 どんなに弁解しても、真っ赤な顔をしつつスプーンで香茶をかき回しながら尻すぼみに言うセリフでは、まったく説得力がない。
アメリアはそんなリナを、可愛いと思いつつ見つめていた。 そして、…なぜリナが、いまだその想いに気づかぬフリをするのかも、わかっている。 (そう、あいつは、神父なのよ―――)
リナは無意識のうちにため息をついていた。
リナが好きだと告げれば、ガウリイは間違いなく悩むだろう。それも、どう断るかについて、だ。 その胸にわだかまる思いを飲みこむかのように、リナはぬるくなってきた香茶を一気に飲みほした。香茶の香りで、胸のつかえまでスッキリするような気がする。
「――ごちそうさま、アメリア。あたしもう帰るわ」
一度だけインバース家の夕食に誘われて、その量の多さを知っているアメリアは、ひくと片頬をひきつらせた。
「じゃーねー、アメリア」
ひらひら手をふりながら大きなかごを片手に出てゆく友人を見送って、アメリアはこっそり息を吐いた。 だが、大事な友人の恋が、うまくいってほしいと思うのも事実である。
信念と友情の板ばさみになり、しかも結局は部外者ということもあって手を出せない自分は、傍観者でいるしかないのだろうか。
「…あれ? どこいるんだろ」
菜園からキョロキョロ見渡すと、ひとつの窓ごしに、教会の中にいるガウリイが見えた。
「ねーガウリイ、なにやってんの?」
がたたん、と少々騒がしい音をさせ、立てつけの悪い窓が開かれた。礼拝堂の冷気がこちらに流れ、外の暑さに慣れきったリナの肌には心地よい。
「さっきまで結婚式があったからな。その片づけだよ」 その名前はリナにも心当たりがあった。2・3度町中で、仲睦まじく歩いているのを見たことがある。そうか、結婚したのか、あの2人。
「ねえ、ガウリイ。あたしも手伝おっか?」 リナは窓枠に手をかけ、ぴょん、と跳んで窓から入った。
「あ〜〜〜っ、お前なあ! その入りかたするなって言っただろ!」 パイプオルガンの手入れを始めるガウリイと一緒に、リナはテープの片づけにとりかかった。
ちょん、とガウリイがリナの頭にグラスをくっつける。 「あ、あんがとガウリイ」
リナは礼を言ってそれを受け取る。口をつけると、ひんやり甘い液体がのどを潤していった。
「リナ、これ持って帰ってくれないか。教会だけじゃ飾りきれんし」 そう言いながらも、花束をもらったリナの顔は綻んでいる。やはり女の子、きれいな花は嬉しいのだ。 「なんだか…ブーケみたい」
本物ではないけれど。それでも結婚式に似合うもの、という基準で選ばれた花。
うつむいて、花を見たままのセリフ。
「そうだな、お前さんもそのうちそうなるかもな。
言ってガウリイは優しくリナの髪に触れる。 「そう、よね……。いつか、そうなるよね……」
小さく呟いて、リナは立ち上がる。 「じゃあ、今日は帰るわ。バイバイ、ガウリイ」
走り出さないように。不自然ではないスピードで。 |
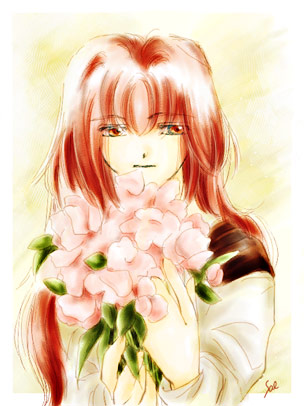 「ねえ。ガウリイ…?」
「ねえ。ガウリイ…?」